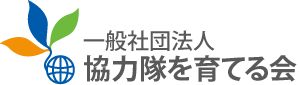|
三人の総理と協力隊
沖縄返還が行われたのが1972年の5月ですから、1992年春のことだと思います。沖縄返還20周年という大きなイベントがあり、国際交流基金の日米センター所長をされていた楠田實さんが世話役になって式典を企画しました。学者グループも協力しろということで渡辺昭夫先生、高坂正堯先生、北岡伸一先生、そして私の4人が動員され、私はオーラルヒストリー(口述歴史)、主に沖縄返還について関係した人が実際にどういう状況で何をしたのかということを日本人、アメリカ人双方にわたって意見を伺うという仕事を仰せつかり、その時に竹下登元総理と話をする機会を得ました。
1992年は冷戦終結直後で、リクルート事件という一大スキャンダルがありました。80年代、日本の頂点を代表するかのような中曽根総理の後に竹下さんが総理に就任、一見地味に見えるかもしれませんが、竹下さんは4年間でいろいろな事をしっかりと定着させる事ができるのではないかと期待されていましたが、リクルート事件に煽られて、2年程でお辞めになりました。その後、あまり予期されていなかったものの、しかし清々しい海部さんが総理に就任されました。更に意外なことに海部さんの後に宇野さんという方が総理になりましたが、そのことを竹下さんは話題にされました。竹下さんは、「竹下、海部、宇野の順番は何の順番か知っているか」と言われ、不思議に思いましたが、これは自民党青年部の部長をされた順番とのことでした。そして、その仕事の中でも青年海外協力隊を作ったということは非常に大事だということを沖縄返還の話を伺いに行ったのに、そんな話題になってしまいました。
私は協力隊については素人なので、協力隊OBの皆さんのように深い経験に根差した話はできませんが、歴史家として協力隊を振り返ることによって本日の勤めを果たしたいと思います。
海外技術協力事業団という一つの柱
協力隊が1965年に発足する3年前、1962年に海外技術協力事業団というJICAの前身が作られました。これが一つの柱になります。
日本は明治時代に「富国強兵」のスローガンを掲げましたが、満州事変以降1930年代は「強兵」へとかなり力が傾いてしまいました。「大東亜共栄圏」などのスローガンもありましたが、改めて考えれば、我々は何のためにあの戦争をしたのか答えに困るような、そういう戦争に継ぐ戦争をしてしまいました。
第一次世界大戦後のベルサイユ条約でドイツは天文学的な賠償金を課せられましたが、それが、わずか二十年で世界的な戦争を招いた一因です。それは英知の平和ではなく、勝者たちの不見識だったとも言えます。敵愾心に満ち、ドイツを絞れるだけ絞れという報復感情に駆られて戦後処理をしたことが、わずか二十年にしてさらに巨大な第二次世界大戦を招きました。
そして、第二次世界大戦の終戦時には、その反省が勝者たちにありました。満州事変から真珠湾まで10年間駐日大使をつとめたアメリカのジョセフ・グル―は、第一次大戦のパリ講和会議にアメリカ代表団の事務局長として参加しています。彼のような心ある指導者たちは、過去の失敗を繰り返してはいけないという思いをもっており、そのことは日本にとって幸運でした。
第二次世界大戦の時は、先進国は基本的に賠償金を放棄、日本は第一次大戦のドイツのように天文学的な賠償金は課せられませんでした。イギリスは一部、香港にある日本の港湾施設を抑えたりしましたが、戦後、日本経済の復興を困難にするような賠償金を課してはならないというのが連合軍の方針でした。また、直接侵略をうけた周辺のアジア諸国は、日本の復興を困難にするものではない一定の賠償を個別に求めるがよいということで、「節度ある賠償」とも言うべき、緩やかな賠償がビルマ、インドネシア等に対して個別に行われました。
日本は1952年に独立を回復しましたが、その直後であり、まだ賠償が終わらない1954年にはコロンボプランという途上国の開発協力に参加しています。日本の経済再生の地平を整えるという思いで有償、無償の経済協力が進められましたが、それは日本にとってもマイナスではないという観点から行われたのだと思います。当初は賠償という戦争への責任からはじめたことですが、実際にやり始めると、情熱を傾ける組織的活動に転じたのだと思います。
ケネディの登場と青年運動から生まれた二つ目の柱
こうした戦後処理がかなり済んだ1960年のことです、私と同じ年配の方は昨日のように覚えていらっしゃるかもしれませんが、ケネディ大統領が颯爽と登場しました。ケネディ大統領は就任演説で「国があなたのために何をしてくれるのかを問うのではなく、あなたが国のために何を成すことができるのかを問え」という有名な言葉を残しています。
ケネディは日本研究の第一人者でハーバード大学教授であったライシャワーに駐日大使として日本に赴き、両国の懸け橋になってほしいと依頼しました。ライシャワーは日本人の奥様ハルさんとも相談、自分が戦勝国の大使として日本に乗り込み、日本にいるたくさんの友人、知人から上からの目線と受け止められたくない、そう逡巡している時に、「国のために何ができるか」というケネディの言葉に心動かされて東京に赴任されたという話を本人から聞きました。そのケネディの理想主義が純化された形がアメリカの平和部隊です。上からの目線で受け手の理解を欠いていたのではないかという反省に立ち、本当に途上国の発展に役立ちたいという思いから平和部隊がつくられました。
米国の平和部隊が刺激になって日本の協力隊が作られたという見方もあります。しかし、大きな刺激になったことは間違いありませんが、それ以前からたとえば青年運動家の末次一郎さんは協力隊の構想を温めていました。私も末次さんとは何度か沖縄返還問題でご一緒させていただいたことがありますが、彼は「健青会」という組織をつくり、終戦直後は引き上げ地の舞鶴で右往左往している帰還兵のお世話をされ、その後も海外での遺骨収集、そして沖縄復帰を民間から支えた人です。
末次さんは1950年代後半頃から健全な青年をアジア支援のために送るべきだと提唱、1960年を迎えるころには青年の海外協力派遣計画を打ち出そうとしていました。その矢先にケネディの平和部隊が発表され、彼はアメリカに先を越されたと悔しがったそうです。
もう一人、末次さんとは別に寒河江善秋さんという山形出身で青年運動をされている方もいました。寒河江さんは、国のために戦争に行き、なんとか生き延びて帰ったのに、周囲からはまるで犯罪者扱いの冷たい視線、母親だけは良く帰ってきたとは言ってくれるものの、殆どが次男三男で田舎では食べさせることもできない、そうした若者たちをこれからの日本の経済社会を支える人材として青年たち自身の手で蘇らせようという運動を展開しました。建設省の協力を得て、約20の県で「産業開発青年隊」という組織もできました。
このように大きく分けて二つの流れがあり、一つは日本の技術をもって途上国の開発のために働こうということに力点をおく国の動き、もうひとつは末次さんや寒河江さんのように民間運動として、志のある若者の育成に重きを置く動きがありました。こちらは外務省の管轄下ではなく、総理直属の組織として世界で奉仕をすることで戦後日本の青年が誇りを持ち、復興を担う人材として育ってほしいという強い思いがありました。
坂田道太氏の裁定
いよいよ協力隊の設立が現実となると、両者の主張の対立は厳しかった様です。これをどう調整するかということで、「困った時の坂田さん」、坂田道太氏が登場することになります。坂田氏は文部大臣を務めた他、ハト派の人に見られがちですが防衛庁長官も務められ、非常に立派な仕事をされ、衆議院議長も務められました。威張らない、飄々とした穏やかな風貌の方で、良識の固まりのような方、やっかいな事がおきると坂田さんの良識に問う、ということが多くあり、どんな大臣をやっても立派な判断を示されました。
防衛大学教授だった佐瀬昌盛というドイツ、東欧の専門家が坂田道太の評伝を書いていますが、その中で協力隊設立の記載もあります。坂田さんの判断は、協力隊は途上国の技術協力を行うという主張はもちろん一理ある。実際の社会に役に立つ技術能力を持っていることは大切である、しかし、それだけならば外務省の技術協力を大規模にやればいい。それ以上のものが青年海外協力隊にはあると坂田さんは考えられたようです。
また、坂田さんはアメリカの平和部隊も視察されていますが、アメリカは英語で民主主義の大義を語ればそれだけで立派だが、日本は英語で民主主義を語ることもできない。だから日本が行う場合には対手国のお役に立てる技術能力をもって行くことが大切である。しかし、技術というのは、それ自体が目的ではなく道具でしかない。技術を通して多くの人々と接し、共にコミュニティの良き友になり、相互理解を深め、友達になる。愛情をもって付き合うための道具が技術である。技術を提供して何パーセント経済が伸びましたということ以上に人の心と心が触れ合う過程、言語、民族を超えての友情にこそ意味がある、そうお考えになりました。そして、実際の仕事は海外技術協力事業団(JICAの前身)の下でやればいいと坂田さんは裁定され、協力隊は異文化社会の人々と共に汗をかく集団として今日に至るまで成長してきました。
ラオスの隊員を視察
協力隊は大都市、中心都市だけではなく、村落のコミュニティに入り込み、現地の人と一緒に考えるという活動をすることになりました。初期には農業や自動車整備、医療等の技術能力が重要視されました。今日は先生として、スポーツ指導者として、ソフトを提供している隊員もたくさんおり、広がりをもっています。
いろいろな隊員の方に伺うと、典型的な隊員というのは、1年目は本当に大変な様です。現地の言葉もまだ不十分、文化も違う。突然投げ出されて途方に暮れる。そんな人が多いようです。しかし、それでも何か意味のあることがやりたいと1年近く活動を続けていると必ず理解者が、上手くいけばパートナーができる。2年目にはパートナーの力を得て仕事が軌道に乗る、そして2年目が終わる時は帰りたくない、必ずまた戻ってくるからと涙にくれる。
私は経験者ではないからわかりませんが、それが典型的な隊員の姿だと理解しました。
最初にご紹介いただきましたとおり、2年前に私は協力隊50年の評価を行い、今後を検討する会議(JICAボランティア事業の方向性に係る懇談会)の座長を当時の田中JICA理事長に命じられました。私だけが協力隊のことをよく知らないと不満を言ったら、では視察に行ってくれと、10日間ラオス北部のウドムサイ県という所に派遣されました。
そこには、6人しか日本人がおらず、しかも全員が協力隊員でした。うち二人はサッカー、バレーのスポーツの指導をしていました。見ていると金魚のフンのように子供たちが隊員の後ろをついてまわっています。先生は非常にきびきびと指導されていました。スポーツの指導をすると同時に挨拶や終わった後の道具の整理整頓を指導されており、こういうことは無意味ではないと感心をいたしました。
また、スチュワーデスをされていたという隊員の活動も視察させていただきました。県庁所在地、といっても信号もないような田舎町で、彼女はその町の絵地図を作っていました。初めてとなる絵地図でこの地の観光振興を支えるべく、活き活きと活動されていました。
任期も残すところ僅かとなった、ある一人の隊員は、山の中の少数民族の村へ私を連れて行って活動を紹介してくれました。そこでは、山の木から取り出した繊維を使い、かねてから籠などの実用品が作られていましたが、隊員は工夫すれば国際的な商品になるとの着想を持ち、活動は軌道に乗って、今ではビエンチャン空港のショップで売れ筋商品になったそうです。もちろんこの地に貴重な収入をもたらしました。
医療関係の隊員も視察させていただきました。環境は決して楽ではないようで、衛生の観点から考えれば改善しなければいけない事が多く、苦労しながらも頑張っていました。
都市計画に関わる隊員は、抽象度が高くて苦労されている印象をうけました。
また、ビエンチャンでも隊員の仕事を見せていただきました。ここでは、メコン川の魚を食べる際、しっかり火を入れないので、内臓をやられてしまう、薬をあげても同じことを繰り返して悪化させてしまうので、過去に日本の医師が寄生虫の予防マニュアルを作られたそうです。時代が経過して古くなってしまったので、その医療面の隊員の方はマニュアルの書き換えをしていました。
視察した隊員の方たちは皆、それぞれに意味があることをしていると感じました。しかし、「颯爽と鮮やかに」という感じではありません。何年か前にウドムサイ県で国体が開催された時、中国がお金をドンと出して大きなスタジアムを作り、そのスタジアムの芝生で日本のボランティアの人がサッカーなどを教えているのです。韓国ではKOICAというボランティア組織があり、ここ一番では改善資金を投入していました。それに比べて協力隊員が扱うお金は僅かな額の自分の生活費が殆どで、言葉は悪いがダンゴムシのように地面を這いつくばっている。中国や韓国のようにもっと目に見える成果が実感できるように鮮やかに活動をしたいという思いにとらわれないだろうか。最後の夕食会で隊員一人一人の意見を聞きましたが、6人全員が日本はこれでいいと言いました。なんとかやれるようになって思うのは、先人たちが築いたこの地の人々との信頼関係、かつての隊員たちが培った信頼関係によって今の自分たちは支えられている。これは50年かけて築いてきたもので、代えがたいものであると。ただ、一人の隊員は、我々はこれだけ現地に深く入り観察して得た知識があるのだから、もっとJICAには有効に活用して欲しい、という意見もありました(後で聞くとそういう制度もあるとのことでしたが)。
日本人の価値は、苦しみながら一緒にコミュニティを支え、目に見える形、あるいは数量化できる形以上の大きな資産を組み立てていることです。本人たちも勉強しながら、そう認識している姿に感銘を受けました。
「戦後日本の価値」を支える協力隊
京都大学の高坂正堯先生は、国際社会を「力の体系」、「利益の体系」、そして「価値の体系」という言葉で説明されています。戦前の日本は、「力の体系」に大きく傾きました。それに反省した日本は戦後、経済国家として「利益の体系」に傾きました。
アメリカの場合をみると、20世紀のはじめにセオドア・ルーズベルト大統領が登場しましたが、彼はまさに「力の体系」の達人でした。ヨーロッパ的な外交感覚をもち、某一国がアジア大陸を支配することを排除しなければならない、しかしアメリカはすぐには行動できないので、苦しんでいる日本をバックアップする、そんな形でロシアの進出を阻止した、「力の体系」の達人でした。ルーズベルトの後を継いだタフト大統領はノックス国務長官に「ドル外交」をやらせ「利益の体系」に非常に熱心で、遅ればせながら経済力をもってアジア大陸に割り込もうとしましたが、日本とロシアの反対に遭って挫折しました。その次の大統領、ウィルソンは宣教師の子であり、プリンストン大学の総長をされた方ですが、彼は初めて声高に「価値外交」進めた人です。第一次大戦の時、アメリカはヨーロッパの戦争には関わらないという方針でしたが、やはり放ってはおけないということで1917年に参戦、その時にウィルソンは、これは「民主主義のための戦いだ」と言いました。世界の平和を確かにするための戦いであり、民主主義、人道、法の支配、そうした普遍的な価値のためにアメリカは立ちあがるのだ、という趣旨の言葉を残しました。私利私欲のためではないと「価値の外交」を打ち出したのです。それ以降、アメリカの全ての政権は、力点の置き方は様々ですが、「力」、「利益」、「価値」すべての体系を持っており、どれかを完全に否定しきることはできていません。個別取引での利益のみを重視し、普遍的価値を否定しているのはトランプ大統領が初めてであり、極めて例外的な大統領の登場に世界は今後どうなるのか懸念されるところです。
戦前、日本は力に頼りすぎ、中国とアメリカという二つの大国に戦争をしかけ、案の定、滅亡しました。そうした歴史を考えれば、21世紀の日本は「日米同盟プラス日中協商」でいかなければならないというのが私の持論です。冷戦期の日本は、安全保障はアメリカの庇を借りて、自らは「利益の体系」に傾き大いに財をなしましたが、冷戦終了後は経済国家としてあまり芳しい状況とは言えません。民主主義や法の支配という価値は、もちろん日本が大切にしているものですが、しかしながらそれは我々が打ち出したものではありません。
しかし、改めて振り返ってみますと、日本は賠償が終わらないうちからODAで途上国を支えてきました。中東に行った時にテルアビブで会ったある方は「もし、どこかの先進国から援助を受けるとすれば日本がいい」と話しました。日本から来た客のための社交辞令とも思ったのですが、彼は本気だと言います。ヨーロッパもアメリカも高みから支援をしてやるから、ひざまづいて受けろという感じになってしまうのに、日本人は地面に膝をついて一緒にやろうと言ってくれる。同じ地面に足をおき、友人として相談にのってくれる、そういう日本の援助を受けたいと言うのです。
円借款は「金貸し業」だと言われることもありますが、日本から見れば、力をつけて自力で果実を出して返してほしい、また返していく余力をつけないと、世界の市場経済の中で自力で生きて行くことはできません。そんな持続力がつくよう応援をするのが日本のやり方であり、それが「東アジアの奇蹟」に繋がったのではないでしょうか。かつて日本以外のアジアの国が経済発展する望みは低いと言われていたのです。今ではアジアはおろかアフリカでも目覚ましい発展を遂げている国もあります。経済合理性の下、上手に発展させていくことが大事ですが、客観的に見て非常に厳しい国も少なくありません。そういうところに対しては、たとえ簡単に成果の見込がなくても一緒に苦しみ、苦労して汗をかく、そういう友人が世界にいるということが大事なのだと思います。
1965年の創設以来、協力隊員はたとえ地味なダンゴムシではあっても、コミュニティに入り一緒に暮らし、苦労して汗をかいてきました。それは戦後日本の価値ではないかと思うのです。戦後日本には「利益の体系」以外ないと言う人もいますが、協力隊は世界に対して貴重な「価値の体系」を提示しているのではないでしょうか。
これまでの協力隊員の皆さんの活動に敬意を表して、そう申し上げたいと思います。
以上
質疑応答
| Q. |
会長を拝命しております山本と申します。青年海外協力隊にしても国際緊急援助隊の評価にしても、現地の評価と日本の評価にはかなりのギャップがあるように感じますが、先生はどのように思われますか。 |
| A. |
大変重要なご指摘だと思います。多分、日本人の謙虚さと関係があるのではないでしょうか。世界のどの国でも、国際舞台で良いことをすれば自国の政府は自慢するでしょうし、メディアも誇らしげに記事を書きますよね。ところが日本は、自国の良いことを偉そうに伝えるということに躊躇いがあるのかもしれません。
特に政府が良いことをした時がそうです。例えば「福田ドクトリン」という政策がありました。アメリカがベトナムから引き揚げた後に、東南アジア全域を支えようと日本が一緒にやっていこうとする姿勢を示した、誇らしいものだという世界からの評価でしたが、日本国内では全く話題になりませんでした。そうなると、国民的な認識の羅針盤は成立しにくいものです。先ほど、ダンゴムシという失礼な言い方をしましたが、若者が草深い所で苦労しているのに、評価もされずに仕事に穴をあけたと怒られたりする。非常に芳しいことをしているのに自己認識できない、自信がもてない。日本にはわりとそういうことがあるのではないでしょうか。そして、外国で評価された途端に賞をあげなければと言い始めたりする。日本のそうしたところが残念です。反射的には褒めてもらえないかもしれませんが、自らの信ずるところ、誇りあるところについては声を大にして言うことも大切だと思います。
総理官邸の昼食会で、橋本龍太郎首相とご一緒にしたことがあるのですが、ODAの10%カットを3年続けるという話になったとき、私は総理にそれは違いますよと反論したことがあります。今更、日本は力を背景に外交する国ではない。そういう国にとって他国を支援するODAは非常に貴重なものであり、そういうものを潰してしまったら、誰が首相になっても充分な仕事ができなくなる、だから考えなおして欲しいと言うと、首相はODAには感心できないものが多いと反論され、議論は並行線をたどり、気まずい空気に終わりました。しかし、その後、総理を辞めた後のインタビューではODAは大切だと言っておられました。 |
| Q. |
大島顧問 先程の話の中で、もし援助を受けるのであれば日本からがいい、という話がでましたが、自分にも似たような経験があります。日本を常任理事国入りに、というキャンペーンをした時に、多くの国が似たようなことを言ってくれました。一番先に常任理事国になってほしい、もちろん外交辞令もありますが、そういう財産を我々は持っていると思います。協力隊の評価にもう少し定量的な指標を、という話もでているようですが、それを超える実績、価値、言い表しにくいかもしれないが、政治に関わる人たちにはもっと自信をもってもらいと思うのですが、如何でしょうか。 |
| A. |
かつて私は、防衛大学の校長をしていたのですが、東南アジアから約100名の留学生を受け入れていました。5年も自国を留守にしたら、その国の本流から外されてもおかしくないのに、今や自国の部署でトップになる人もでてきています。そうしたことへのお礼に東南アジアの5カ国を回ったのですが、当時は東日本大震災の後だったので、どこに行っても、私は心のこもった支援への御礼から会談を始めました。それに対し、我々こそ日本のODAで本当にお世話になった、それを思えばほんの感謝のしるしでしかないという言葉で返してくれました。感謝の言葉を言わないのでODAをやめてしまえという声もあるようですが、いちいち気にせずに、しっかりやるべきことをやり、思いがけない時に帰ってくれば、それでいいのではないでしょうか。政治家は支持率、テレビは視聴率を神様にしていますが、本当に大切なものは数量化できないという感覚を、国民は失ってはいけないと思います。 |
|