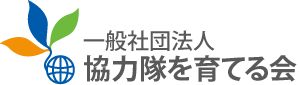あいさつ
本日は、育てる会の総会にお招きいただき、ここでお話ができることを嬉しく、また光栄に思います。
元々、自分は外務省の人間でJICAに対しても一宿一飯の義理があり、JICA関係者の方々とお会いすることをいつも楽しみに思っています。
また、今回は北海道から九州まで、全国の育てる会の役員の方が参加されていると聞いています。協力隊事業も様々な問題を抱えているようですが、全国の育てる会の方がそれぞれのお立場で協力隊事業をサポートしていただいているということは、大変心強いことです。私が言うのは変かもしれませんが、これからもぜひ協力隊事業のご支援をよろしくお願いします。
さて、本日の演題は、まるで小説のタイトルのようになってしまいましたが、最初に申し上げたいことは、上皇上皇后両陛下がこれまで行ってきたお仕事全体の中で見ても、協力隊事業に対しては、特別な意味があることだと私は思っています。
協力隊の話の前に、まずは両陛下が行ってきた全体のお仕事からお話ししたいと思います。
「天皇の役割」について
 皆様ご承知のとおり、天皇陛下(平成天皇)は1ヶ月前に退位され、上皇陛下となられました。5月1日から新天皇が即位され、新天皇がお仕事をされているご様子はテレビ等でも周知のとおりかと思います。その一方で、上皇上皇后両陛下の動向については、ぱったりと報道も途絶えました。実際に公式の日程というものは殆どなく、比較的ゆっくりとした日々をお過ごしになっていらっしゃることかと思います。 皆様ご承知のとおり、天皇陛下(平成天皇)は1ヶ月前に退位され、上皇陛下となられました。5月1日から新天皇が即位され、新天皇がお仕事をされているご様子はテレビ等でも周知のとおりかと思います。その一方で、上皇上皇后両陛下の動向については、ぱったりと報道も途絶えました。実際に公式の日程というものは殆どなく、比較的ゆっくりとした日々をお過ごしになっていらっしゃることかと思います。
まずはお引越しの準備をしなければならないし、30年間働き続けてきたので、時間をかけてこれから新しい生活の展望をつくっていかれるのだろうと思っています。とりあえず6月11日〜13日にかけては京都に行かれて、退位されたことをご先祖に報告されると聞いていますが、その先のご予定については我々にも分かりません。
さて、今年の4月30日までの30年余り、陛下は日本国憲法の下、象徴というお立場で天皇としての務めをされてきました。この象徴というお立場に初めからなられたのは、今の上皇陛下が初めてです。昭和天皇も後半生は日本国憲法の下での象徴としてすごされましたが、物心がついた時からというわけではありませんでした。陛下は記者会見等の席で、「天皇の役目」というものについて何度もご質問を受けていますが、その度に「自分はそれを模索しながらやってきた」という趣旨のご返事を終始一貫して続けてこられましたし、確かにそうだったのだろうと私も思います。
3年程前、「天皇の務め」について紹介したテレビ番組が放映されましたが、その中で、陛下は「天皇の務め」というものをご自身なりに整理してお話をされており、「天皇の務め」には大きく二つあるということをおっしゃっていました。
一つは、「国民の幸せを祈る」ということです。「祈る」ということが形として見えるのは、宮中三殿でのお祈りなど伝統的なものがありますが、基本的に祈るということは心の中の問題であり、外から見てもわからないものです。「祈る」というよりも「願う」と言ったほうがいいのかもしれませんが、陛下は常に自分のことよりも国民の幸せのことを気に掛けておられたことは、ご一緒にいたのでよくわかります。
もう一つは、「人々の傍らに立ち、その声に耳を傾け、その思いに寄り添う」ということを言われています。やや抽象的な話ですが、東日本大震災の時には、確か7週間ほど連続で、毎週一度、日帰りで被災地のお見舞いに行かれましたが、あれが「人々の傍らに・・・」ということであったのだと思います。
「人々の傍らに立つ」ということは、ただ皇居の中で祈っているのではなく、自分を必要としている人のそばに行くという意味です。「耳を傾ける」というのは、家族が津波にさらわれたとか、家が流されたとか大変なことがおこり、辛い思いや悲しい思いをしている方が誰かにその思いを訴えたいと思っている時に聞く、ということです。一方的にこちらの考えを言っても、その人にとって本当の慰めにはならない。徹底して聴くということが本当の慰めなのだと考え、陛下は実際にそうなされているのだと思います。そして最後に「人々の思いに寄り添う」というのは、その人たちの思いをできるだけ理解して近づこうということだと思います。たとえ全く同じ思いにはなれなくても限りなく近づくことはできる、そう思われているのだと思います。
陛下の「慰霊」への想い
もう少し具体的にみると、それはたとえば戦没者の慰霊という形になります。陛下は皇太子の時代に日本人が覚えておかなければならない日が4日あると言われました。それは6月23日(沖縄で組織的な抵抗をやめた日)、8月6日(広島原爆投下の日)、8月9日(長崎原爆投下の日)、そして8月15日(終戦記念日)です。これは戦争の惨禍が一番激しかった場所であり、それらの日には陛下ご自身も黙祷をされています。平成7年に戦後50年を迎え、その4つの被災地をなぞるような形で、沖縄、長崎、広島、東京を訪れ、慰霊しています。それが終わりしばらく経った後、陛下は、今度は国の外で慰霊をされたいとおっしゃりました。具体的には南太平洋で慰霊をされたいと。その時、私はすでに侍従長となっていましたが、物理的に南太平洋の訪問は難しいと申し上げたのですが、何回言ってもあきらめるとは言われませんでした。そのうち根負けして現地に行って調べてみたのですがが、やはり滑走路の問題、宿舎の問題、自動車の問題等、いろいろな問題があり、陛下が訪問されることで先方に負担をかけてしまうので、よろしくないということを申し上げたことがあります。陛下は、それでは仕方がないと諦められたと思っていたのですが、少し経った後、ではサイパンなら大丈夫ではないかと言われました。確かにサイパンだけならば受け入れは可能だったので、2005年にサイパンを訪問されました。「バンザイクリフ」でお祈りされる両陛下の写真が有名なので、覚えている方も多いと思います。それで南太平洋の話は終わったと思っていたら、さらに10年経った戦後70年には(この時はすでに私は侍従長の職を離れていましたが)、パラオをご訪問されました。10年も経つと南太平洋の状況も改善されていましたが、それでも陛下がご宿泊できるような場所はなく、結局海上保安庁の巡視船で一晩泊られました。また、ペリリュ―島まではヘリコプターを使われるなど、大変なご旅行ではありましたが、両陛下はとにかくやり遂げられました。これは実に陛下らしいエピソードで、やろうと思ったことを最後までやり遂げる、物事のなさり方であろうと思います。
こうした慰霊の旅の結果、慰霊の対象も日本人の被害者だけでなく、敵側の人間として倒れた人、戦争に巻き込まれた現地の人等、すべての方の慰霊をしたいと言われました。(本日は、沖縄からはいらしていないようですが、沖縄の話をすると時間が無くなってしまうので、またの機会にしたいと思います)
また、陛下は震災や戦災に巻き込まれた方ばかりでなく、たとえばハンセン病の療養施設13か所をすべて回られるなど、障害者の方等に対しても特に心にかけて慰めてこられました。結局なさってきたことの非常に多くの部分は、社会の真ん中で元気にやっている人ではなく、いろいろな事情によりむしろ特別の苦しみや悲しみをもっている、そういう人たちを力づけることが、両陛下がなさってきたことではないかと思っています。
協力隊に関心を寄せられる4つの理由
さて、そうしますと、協力隊に対するご関心、励ましというのはある意味、特別なことなのかもしれません。最も元気な若い人が、しかも外国に行って仕事をする、そんな人たちを励ますというのは妙に思えるかもしれませんが、それにはやはり意味があるのだと思います。
1965年に協力隊が設立され、最初の隊員がラオスとカンボジアに赴任、その後、マレーシア、フィリピンの第1次隊員が出発されました。最初の隊員のご接見は9名という人数でしたが、それ以降、出発隊員はどんどん数が増えていきました。しかし、いくら人数が増えても、両陛下は彼等のご接見をやめられようとはしませんでした。平成7年度が最後だと記憶していますが、出発隊員のご接見を皇太子に譲られた後も、今度は帰国隊員の代表と1年に二回、会われてお話を聞くということを新たに始められ、隊員たちとのご接見はまったく切れ目がなく続いてきました。
では、ただ関心を持っているというだけではなく、実際に彼等とお会いになって話を聞き、励まし続けてこられたのは何故なのでしょうか。
そもそも協力隊が何故できたのか、いろいろな考え方があると思います。末次一郎さんを代表とする青少年育成という考え方、国際交流という考え方、技術移転としての考え方、そうしたもの全部が一体となり、人間の熱意や情熱といったものがこれまで協力隊事業を動かしてきたのだろうと私は思います。
1985年、協力隊発足20周年記念式典の場で天皇陛下(現上皇陛下)がお言葉を述べられているので、その一節をご紹介したいと思います。
「協力隊の活動の一つ一つは極めて地味なものであります。しかし、それが積み重ねられていくとき、任地の人々とその社会に幸福をもたらしていくものと期待されております。したがって協力隊の活動は日本人が世界に寄与していく誠に意義深い活動であります。それと同時に、日本人の中に協力隊員を通して任地の人々を理解し、心を通わせる人々が育っていくことも非常に頼もしく感じられます。」
このお言葉は、非常によく協力隊の本質を表していると思います。
何故、両陛下がこれまで協力隊を支援してこられたのか。「理由」というよりは「想い」と言った方がいいのかもしれませんが、大きくわけて4つあると思います。
一つは、上皇陛下が考えられている国際親善というお考え。いろいろな考え方はあると思いますが、上皇陛下は、一人一人の人間が相手の国の一人一人の人間と知り合って心を通じ合い、それが積み重なっていくことが全体として国際親善となり、ひいてはそれが世界の平和の基礎にもなる、そういうお考えをお持ちだと思います。まさに協力隊の仕事はこの枠にはいるのではないでしょうか。
二つめは、いわゆるボランティア精神によるサポート。ボランティア精神というのは、性格付けるとすれば、「無償の」「人のための」活動です。日本では特に大災害がおこると、他の地域の人々がボランティアとして助けるということが浸透してきましたが、これは昔から陛下がそうであるべきだと言われてきたことですし、最近はそれが広がってきたことをうれしく思っておられる筈です。
三つめは、青年というものに対するご関心であろうかと思います。皇太子時代には、自分と同年代の日本人が何を考えているのかお知りになりたかったのだろうと思います。これは国内での話ですが、皇太子皇太子妃として地方を訪ねられた時、お二人は殆ど必ずといっていいほど若い人に集まってもらっていました。農業に携わる人をはじめ、いろいろな職業の人たちと懇談されています。協力隊の場合、海外に行って活躍しようとしている青年に対する関心、期待があって話をしたい、報告を聞きたいという想いで続けてこられたのだと思います。また、だんだんとお年をとってきた後も、若い人と会う機会を常に大切にされてきました。私が侍従長の時代、いわゆる「負担軽減」という問題がありました。陛下があまりにお忙しいので、仕事を減らすことを考えたのですが、結局成功しませんでした。ある会合などについては、もういいのではないでしょうかと進言したところ、陛下は「それでは若い人と会う機会が無くなってしまう」と受け入れてくださいませんでした。
そして最後の一つは、一人一人の人がアフリカや中南米で何をしているのか、そうした個人の活動に対する本当の意味での関心、あるいは好奇心をお持ちだったのだと思います。それは両陛下とも非常に強く、出発前、出発後、あるいは海外視察の際に会った隊員一人一人に対して、具体的な関心を示されて質問をされていました。また、質問された方も両陛下が実にいろいろなことをご存知であることに驚き、感心するということもよくあったと思います。
今申し上げた4つの理由があわさったようなものとして、両陛下は協力隊のことを常に心の中に抱き続けてこられたのだろうと思っています。
両陛下と協力隊員との様々なエピソード
講演会が終了した後の交流会の場で、協力隊と皇室の記録をまとめた『薫風記』という冊子が披露されるとのことで、事前にJICAから拝見させていただきました。
『薫風記』の中には、陛下と隊員との様々な交流エピソードが納められていますが、その一つにマレーシアに行かれた時、水族館で働いていた隊員が陛下に魚の説明をされたエピソードが記載されています。隊員が「ネコサメです」という説明をしたら、陛下は「それはネコサメではない」というご指摘をされていました。陛下はご存知のようにハゼの研究をしており魚類には詳しく、こうしたエピソードをたくさん残されています。
協力隊とは直接関係がありませんが、つい最近も上皇后陛下が安野光雅という画家が描いた麦の絵が削り込まれたコップをお客様の接待のためにおつくりになられました。コップが完成し、ある方が皇后陛下に持ってきた時に「陛下にもお見せして」ということになり、その方が喜んで陛下に持って行ったところ、陛下は「これは大麦か、小麦か」とおっしゃったそうです。「英語でも大麦と小麦は違うでしょう」と。そうした話は数多くあります。陛下はとてもまじめに科学の話をされているのですが、言われた方は困ってしまう。「たくまざるユーモア」とでも言うのでしょうか。
協力隊員の話にもどりますが、言い話だと思ったことがあります。ガーナに赴任を予定されているある隊員が皇后陛下とお話をしている時に「お母さんに手紙を書きなさいね」、という話をされ、隊員はとても感心したと言っていますが、皇后陛下には確かにそういうきめ細かいところがあると思います。
また、両陛下がケニアにいらした時にナイロビで晩餐会が催され、そこでケニアの元隊員が書いた詩を陛下がスワヒリ語のスピーチで読み上げたという記事があります。『薫風記』には、その詩の内容まで書かれていますが、今でも残っているのか分からないようなので、ぜひ探して欲しいものです。
また、天皇陛下になられてからの話ですが、外国の要人が来日した際、要人の方を招いて宮中晩さん会を開催した際に、協力隊員を話題にされたことが数多くあります。私が記憶しているだけでも、南アフリカのマンデラ大統領がいらしたとき、それからモロッコの王様がいらした時、もっと最近ではフィリピンの大統領がいらしたときに、陛下は晩餐会で協力隊の話をされています。
私が侍従長を拝命したのは平成8年の時ですが、それから2、3年が経ち、ご即位10年となり、いろいろな所でお祝いの会が催されました。たしか「ご即位10年とご成婚40周年を祝う会」が広尾でも開催されました。私自身が侍従長の時の直接の経験です。理事長の先導のもと、帰国隊員の報告があり、私もそれに陪席しました。隊員たちは皆、写真などを両陛下にお見せしたりしてとても話が盛り上がり、話題がなくなるなどということは全くありませんでした。むしろ時間が足りなくなるようなことばかりです。この時にはシニア海外ボランティア、日系社会ボランティアの方々も含まれていたとおもいます。
そして、これは協力隊とは異なりますが、同じJICAが行うボランティア事業の関係で、横浜の移住資料館の話もしたいと思います。両陛下は日系人に対しても特別な想いをお持ちになっています。日系人の方は、もともとは日本人でしたが、それが外国に移住した結果、日本ではされないようなご苦労をされました。生活環境をはじめ、非常に大変なご苦労の中で順応し、立派な社会的地位を築かれた方が大勢います。ハワイ、カリフォルニアの他、先に話をした南太平洋は第1次世界大戦の後に国際連盟による日本の委任統治の下、沖縄をはじめ多くの日本人が移住し、やがて大統領も輩出しました。慰霊のこともありますが、日系人のこともあり、陛下の南太平洋への感心はとても高いのです。また、最近ではフィリピン、ベトナムなど、戦後、現地に残された日本人のことにも感心をもたれています。
昔からサンパウロ、ロサンゼルスなどには、日系人の立派な博物館があり、日本にもこうした博物館をつくるべきだと両陛下はかなり以前からおっしゃっていました。そうした中、JICAが横浜に移住資料館をつくられたので両陛下はとてもお喜びになり、お二人でご訪問されました。私の記憶が間違いでなければ、「戦争花嫁」についての特別展が開催された時には、皇后陛下お一人で訪問されたと思います。「戦争花嫁」は、ある意味で特別な環境から生まれたもので、日本人はもっと感心をもつべきだと昔から言っておられました。緒方理事長の時だと思いますが、皇后陛下はその展示をとてもお喜びになられていました。
自身の協力隊員とのエピソード
最後に私自身の話をしたいと思います。
 私はJICAの理事をしておりましたが、特に協力隊との関係をお話するとすれば、やはりネパールの話をしたいと思います。1992年にタイ航空の飛行機がネパールのカトマンズで着陸に失敗、山にぶつかって深い谷底に墜落するという事故がおきました。その時の飛行機には、ネパールのJICA事務所で働く職員とご家族、協力隊員、他にも専門家の方が乗られていました。専門家の方というのは、神戸の大学で検査技師をされていた方ですが、定年となり余生を開発途上国のために捧げたいと思われ、御縁があってカトマンズにあるJICAの支援を受けたトリブバン病院というのがあるのですが、そこに行ってネパール人の検査技師を育てたいという志を立てられました。日本ですべてを引き払い、ネパールで骨をうずめる覚悟であったそうです。その専門家の方は、まさにその赴任の途中に事故に巻き込まれてしまいました。お嬢様が一人おられ、彼女は一人では心細いので婚約者を同行させたいと言われました。総務担当の理事として私がご遺族の方たちをカトマンズまでお連れすることになったのですが、当時のJICAの規則では婚約者の同行は認められていませんでした。それではあまりに可哀そうなので、なんとか手を尽くして同行いただくことができました。 私はJICAの理事をしておりましたが、特に協力隊との関係をお話するとすれば、やはりネパールの話をしたいと思います。1992年にタイ航空の飛行機がネパールのカトマンズで着陸に失敗、山にぶつかって深い谷底に墜落するという事故がおきました。その時の飛行機には、ネパールのJICA事務所で働く職員とご家族、協力隊員、他にも専門家の方が乗られていました。専門家の方というのは、神戸の大学で検査技師をされていた方ですが、定年となり余生を開発途上国のために捧げたいと思われ、御縁があってカトマンズにあるJICAの支援を受けたトリブバン病院というのがあるのですが、そこに行ってネパール人の検査技師を育てたいという志を立てられました。日本ですべてを引き払い、ネパールで骨をうずめる覚悟であったそうです。その専門家の方は、まさにその赴任の途中に事故に巻き込まれてしまいました。お嬢様が一人おられ、彼女は一人では心細いので婚約者を同行させたいと言われました。総務担当の理事として私がご遺族の方たちをカトマンズまでお連れすることになったのですが、当時のJICAの規則では婚約者の同行は認められていませんでした。それではあまりに可哀そうなので、なんとか手を尽くして同行いただくことができました。
また、ネパールの山奥ということで、登山の準備、テント、非常食等が必要かもしれないということで、またたく間に準備を整えたJICAの機動力に大いに感心したことを覚えています。こうした経験は、今も緊急援助隊に引き継がれていることかと思います。
しかし、皆でネパールまで行ったものの、事故現場まではとても行くことができないということが次第に分かってきました。もちろん、ご遺体と対面したいというのがご遺族の強い希望です。しかし、いくら待っても結局ご遺体は戻せないということがはっきりしてきました。信濃町の近くに千日谷会堂というお寺があるのですが、協力隊との縁があっため、そこのご住職もネパールまで同行してもらっていました。夏の時期だったので、ご住職は、「もうすぐお盆になるので、むしろ日本に戻ってお盆を迎えよう」という話をされて皆を説得されました。そんな時にネパールに赴任していた協力隊員たちが、飛行機の墜落現場まではいけないものの、谷底の川から流れ出る水場の近くまでいき、そこで洗われている小石を拾ってきてくれました。ご住職は、「この小石には亡くなった方の魂が宿っている」と言われ、それでご遺族の方は皆、納得して日本に帰国されました。
協力隊の皆さんは良くやってくれた。感心した、という想いが今でもあります。
いろいろと辻褄があわないこともあるかもしれませんが、私の話はこれで終わりにしたいと思います。
以上 |